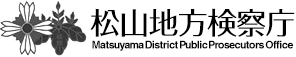裁判員制度
最終更新日:2020年8月27日
明日の裁判員は貴方かもしれません
裁判員制度について正しく理解しましょう
1 裁判員制度とは?
国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒に、一定の刑事事件の第一審の裁判に立ち会って、有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑が相当かを判断する制度です。
- 国民って?
- 20歳以上の、選挙権を有する国民のことです。
- 一定の刑事事件って?
-
殺人、強盗致傷、現住建造物等放火といった重大事件のことです。
通常の交通事故や窃盗、傷害事件はこれにあたりません。 - 第一審の裁判って?
-
全国の地方裁判所で実施される裁判のことです。
控訴審(高等裁判所)や上告審(最高裁判所)はこれにあたりません。
1つの裁判での裁判員の人数は、原則6名です。
2 裁判員は何をするの?
裁判員に選ばれると、その日の午後、あるいは数日後(ただし、土日祝日をのぞく)の朝から法廷で開かれる審理に立ち会い、裁判官や他の裁判員と議論をし(これを「評議」といいます)、有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑が相当かを決めます(これを「評決」といいます)。
裁判長が判決の言い渡しをすると、裁判員の任務は終了です。
- 審理って?
-
審理では、採用された証拠の内容について、見たり聞いたりします。
証人尋問や被告人質問では、自ら質問をすることもできます。 - 裁判官や他の裁判員と議論って?
- 論議とはいっても、特別難しいことではありません。専門用語や法律的な概念はもちろん、わからないことは裁判官が説明します。
- 評議って?
-
評議は別室で行われますが、非公開です。
ここで行われたこと、例えば、誰がどんな発言をしたか、どういう経緯で判決が決まったか、その他裁判員や事件関係者のプライバシーに関することを他人に話してはいけません(これを「守秘義務」といいます)。
3 裁判員にはどうやって選ばれるの?
- 1 毎年・秋
- 選挙人名簿を基に翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。
- 2 毎年12月ころ
- 裁判所から、裁判員候補者名簿に名前が載った人へ、名簿に記載されたことの通知が届きます。
- 3 翌年1月以降
- 裁判員裁判の対象事件が起訴され、その後に行われる公判前整理手続で審理日程が決定されます。
- 4 第1回公判期日(審理の第1日)の6週間前
- 裁判員候補者に呼び出しの通知が届きます。
- 5 呼び出し当日
- 裁判員の選任手続きが行われ、裁判員(及び補充裁判員)が選ばれます。
ここをクリックすると、裁判員が選ばれる手続きのタイムスケジュール(PDF)が見られます。
- 裁判員候補者名簿って?
-
裁判員候補者名簿に記載される方とは、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿の中からくじで選ばれた方です。
この裁判員候補者名簿に記載された方は、翌年1月から始まる1年間は裁判員に選任される可能性があります。 - 通知って?
- 裁判員候補者名簿に記載されたという通知を受け取った段階では、まだ裁判所へ出向く必要はありません。
- 公判前整理手続って?
- 公判(審理)が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人が打ち合わせをして、事件の争点や法廷で取り調べる証拠を整理し、迅速かつ円滑に公判が進行できるようにする手続きです。(非公開)
- 裁判員候補者って?
- 事件ごとに50~100名、呼び出されます。
- 選任手続きって?
- 選任手続きには、裁判官、検察官及び弁護人が立ち会います。
- 補充裁判員って?
- 補充裁判員とは、裁判員が裁判の途中で事故、病気等で参加することができなくなった場合に備えて選任される控えの裁判員のことで、裁判員同様に審理に立ち会うことになります。
なお、裁判員候補者、裁判員、補充裁判員に選ばれたことを不特定多数の人に公表してはいけません。
例えば、ブログ等に書き込むことも不可です。
4 裁判にはどれだけの日数がかかるの?
それぞれの事件の内容により異なりますので、一概には言えませんが、多くは5日以内で終わっています。
5 日当や交通費はもらえるの?
日当は上限が1万50円まで(選任手続のみに出た方にも上限が8,050円まで)支給されます。
交通費や、遠方の方で宿泊を余儀なくされる方には宿泊費用も支給されます。
ただし、公共交通機関を利用した場合の最も安価な金額が支給されます。
6 裁判員になれない人とは?
- 一定の前科のある人
- 心身の故障のため裁判員の職務を果たすことに著しい支障のある人
- 裁判官、検察官、弁護士等の司法関係者
- 国務大臣、国会議員、自衛官
- 大学、大学院の法律学の教授
などの方です。
7 裁判員を辞退できる人とは?
- 70歳以上の人
- 学生
- 過去5年以内に裁判員等をした人
- 親族・同居人の介護・養育の必要がある人
- 仕事上の重要な用務があって、自分が処理しなければ著しい損害が生じるおそれがあるとき
などの方です。